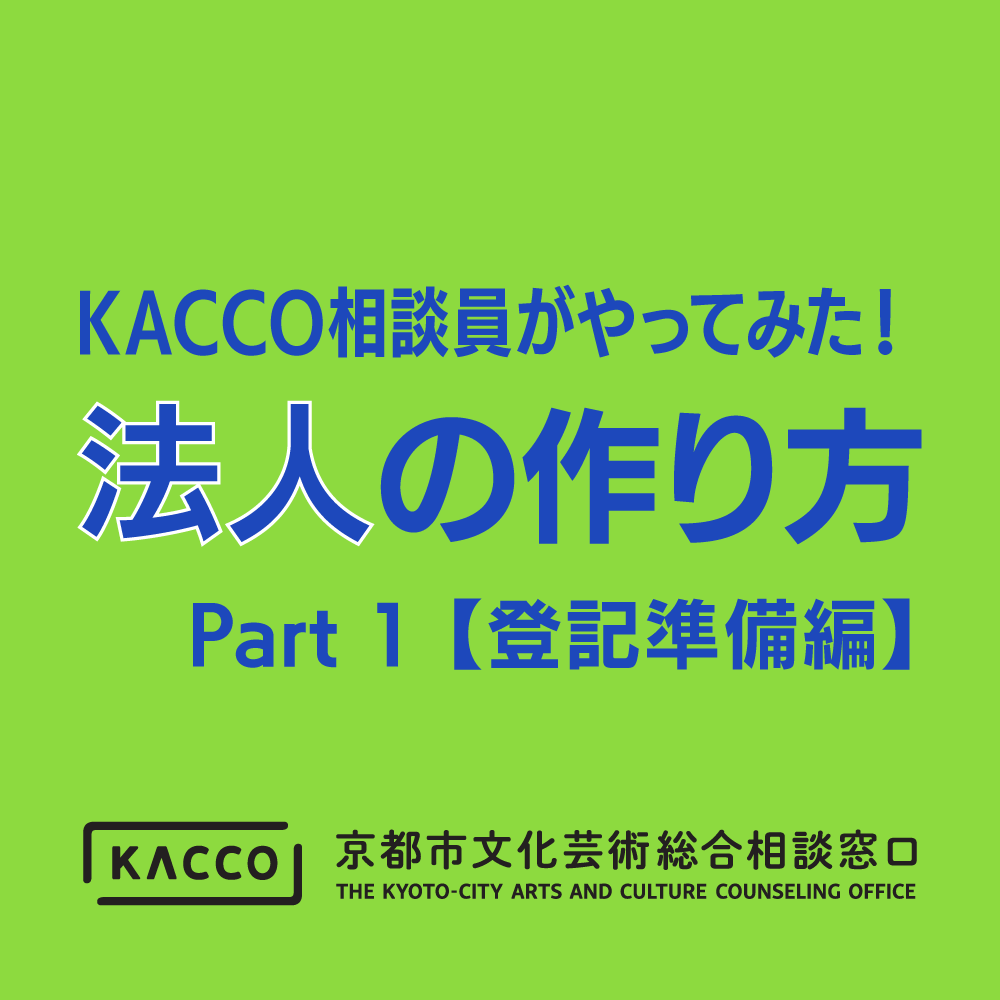presented by KACCO
関連記事
先輩に聞いてみよう!団体の作り方インタビュー
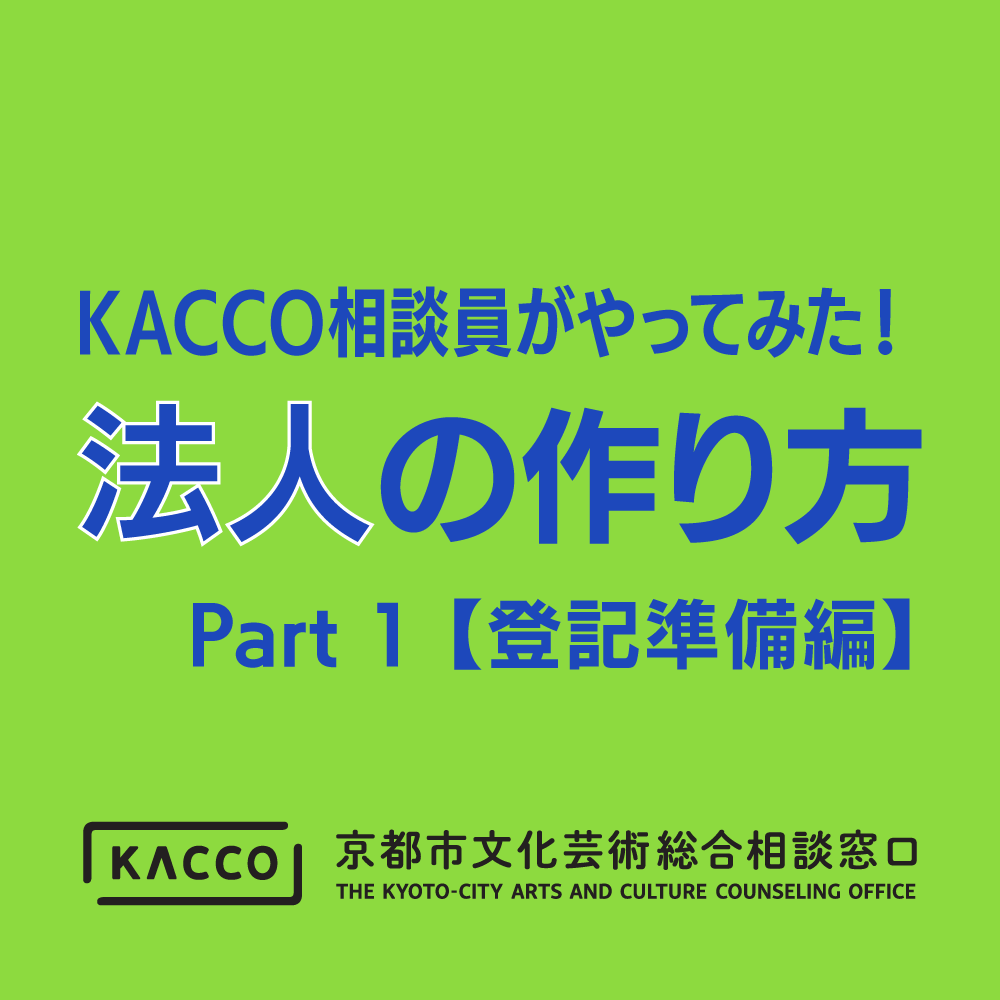
本記事の執筆者は、
京都市文化芸術総合相談窓口(愛称:KACCO)で相談員を務めている、とある音楽家です。KACCOでは、文化芸術関係者の皆様からのさまざまな相談を受けていますが、団体の運営や、法人の立ち上げに関する質問をいただく機会も多いです。KACCOで部分的に回答できることもありますが、より詳しく疑問に答えてくれそうな、他の窓口を紹介することもあります。そんな「他の窓口」の一つ、「
アート×ビジネス共創拠点「器」」に、自分が実際に相談したうえで、法人の立ち上げに至った記録を記事にしてお届けしたいと思います。皆さんの団体運営、あるいは法人化の検討材料として、参考にしていただければ幸いです。
1. 任意団体の法人化を決意するまで
私の運営する音楽団体(ロゼッタ)は2017年に結成した、現代音楽の演奏を主な活動とするアンサンブルです。京都芸術センターCo-Programで結成公演を行なった2018年以来、国内外の作曲家と共同し、精力的に活動を続けてきました。
結成時には活動を10年以上続けることを目標としていましたが、少しずつメンバーのライフステージが進んできたこともあり、足並みを揃えて活動をすることが難しい場面も増えてきました。今回の執筆を担当しており、ロゼッタの主宰者である私自身も、一人で団体のために多くの作業をこなすのが困難になってきたこともあり、今後計画的に活動を継続していくための方策として、法人化を考えました。
2025年5月に、久々に大きな事業となったコンサートを終えた後、打ち上げにて一部メンバーに法人化を提案しました。その後、改めてミーティングの機会を設け、みんなの活動を相互補助できるような仕組みを作り、安定した収入を生み出しながら、より長いスパンで活動していくビジョンを共有したところ、全員あっさりと法人化に賛同してくれました。あんまりあっさりしていたので面食らったほどです。ただし、法人を作ることで何が変わるのか、ということを自分自身も含め、この時点でメンバー全員がはっきりと理解できていたわけではありません。私個人の本音を言うと、ロゼッタという団体にきちんとした人格を与えたい、という理念的な気持ちも強かったと思います。
しかし、法人を作るからには理念だけではなくしっかりとした計画も大事そうだな、と思いました。そこで、まず最初に法人形態を検討しました。私たちは利益を上げることではなく、芸術活動・芸術普及活動を続けていくことを目標にしていることから、非営利法人の一種である「一般社団法人」を立ち上げることにしました。非営利法人と言っても、収益事業をしていけないわけではありません。稼いだお金を分配することはできませんが、そこから定額の給与をもらうことはできます。一般社団法人に見合った事業内容で収益を上げながら団体を継続する方法を考えていくことになりました。子育て中のメンバーが多いことや、こどもや障害者と一緒にアートを作ったり、サポートをするメンバーがいることから、誰もが分け隔てなく芸術を鑑賞したり作ったりするサポートをしながら収入が得られる方向性や、それに関わる芸術家を育成する事業など、様々な案をまとめました。この頃から、子ども向けのコンサート企画を実施するなど、プロトタイプ事業をスタートさせたり、資格を取得したり、少しずつ準備を進めていきました。
別の非営利法人(NPOや財団法人)に参加しているメンバーはいましたが、自分たちが中心になって法人を立ち上げるのは初めてのことです。そこで、京都芸術センター内に設置されているアート×ビジネス共創拠点「器」に相談することにしました。
2.器での相談
「器」での相談では、相談員の山本さん・高坂さんに加え、起業支援を行う企業
ツクリエの笠島さんと、社長の鈴木さんが主に相談に乗ってくださいました。事前に見よう見まねで3年分の事業計画をまとめ、器の皆さんにも共有した後、当日はメンバー全員が現地・オンラインで参加しました。
資金計画は保守的に
事業計画を他人に見てもらう、というのは普段の活動ではなかなか訪れない機会です。全員がかなり緊張して臨んだのですが、最初に事業計画について肯定的なコメントをいただき、一同ほっとしたうえで面談が進んでいきました。鈴木さんからはまず、資金繰りに関して「収入と支出は保守的に見るべき」とのアドバイスをいただきました。「保守的」というのは、収入をたくさん得るような楽観的な予測を避け、過去の実績などに基づいて現実的な範囲で控えめに見積もるということ。支出についても、予期せぬ費用が発生する可能性を考慮し、多めに見積もることが重要だということです。逆に、メンバーの報酬に関しては、かなり少なく設定していましたが、利益が出過ぎると税金がかかるため、ギリギリ赤字を狙う程度の報酬設定が良いということでした。
ルールは「憲法」を作るように
組織運営に関しては、「お金と理念、意義など柱の部分をしっかりと話し合うプロセスを持つこと」が重要だというアドバイスをいただきました。これは、組織の「憲法」を作るようなもので、メンバー間で十分に議論し、合意形成を図る必要があるということです。また、各々のスキルや経験、人脈を「足し算するのではなく、掛け算すること」で、組織としての力を高めることの重要性を強調されていました。私たちが、ギター、マンドリン、サクソフォン、左手ピアノなど、元々普段は一緒に演奏することが少ない楽器同士が集まって作ったアンサンブルであり、音楽活動でも重視しているポイントが法人運営にも応用できることを実感できました。
利益をあげている人に応援してもらう
芸術に関しては補助金や助成金が多くありますが、それに頼っている状態も危ないというご意見をいただき、「企業や利益を出している団体に応援してもらう状態を作る」ことが重要だというアドバイスをいただきました。演奏家としてのスキルだけでなく「法人の理念をアピールし、共感を得ること」が必要です。ついつい演奏が良ければ全てがOKという感覚になりがちな音楽家の集まりなので、肝に銘じておく必要を感じました。また、賛助を求めて営業する際のコツとして、企業の社長さん相手に「松竹梅」のプランを用意すると、真ん中の竹を選んでくれることが多い、というような現実的なアドバイスもいただきました。
メンバーの不安と疑問
相談中には、各メンバーから法人設立に対して漠然とした不安の声が上がりましたが、事業計画をプロの目線で肯定的に捉えてくださったこと、同時に様々な事例を交えながら現実的なアドバイスをくださったことで、法人運営の道筋を現実的に確認できたことが、メンバー全体の安心感に繋がりました。
また、「法人とは書類上の人格を作ること」や、「法人の理事としての自分」という新しいキャラを作って、自分個人で受けられない仕事をそこで受けてしまうとか、お金を稼ぐ仕事とやりたい仕事を混同せずにしっかり分けたり、新しくみんなで遊び場所を作って設計するような気持ちで、法人を楽しみながら作っていくのが良いというアドバイスを、締め括りにいただきました。
今回の相談では、漠然とした不安、はっきりとした不安両方に対するアドバイスに加え、法人をどのように楽しむか?という問いかけで終了したことで、自分たちがしっかり考えていかなければならない部分をポジティブな形で提案していただき、グッと土台を踏み固めてもらったような機会となりました。メンバー全体にも安心感が生まれたことを実感しました。
3. 一般社団法人設立に向けた本格的な準備
定款づくり
事業計画の部分や、メンバーの不安もある程度解消できたので、次に設立に必要な実務作業を進めていきました。まず、取り掛かったのは定款作りです。定款を作るのも初めての作業でしたが、様々なテンプレートや書籍を参考に、Google Document上で書き進めながら、わからない部分はWebで検索したり、AIに質問したりしながら、徐々に内容を固めました。特に公証役場を運営している
日本公証人連合会のテンプレートを骨組みとして使いました。
一般社団法人の基金制度
次に悩んだのは、資金集めに関しての取り決めです。一般社団法人では出資金を募ることができないので、「基金制度」を活用することにしました。基金とは、法人のメンバーや外部の方から、贈与ではない形で資金を調達することができるようにする制度です。利益が出た時に配当を行う出資金と違い、あらかじめ定款の中で条件を定めてお金を預かり、後に返還する制度で、利子も発生しません。一般社団法人は任意でこの制度を利用することができます。基金制度を利用するためには、理事会を設ける必要があり、理事会には3名以上の理事と1名以上の監事が必要です。この部分に関しても、定款でしっかり定めなければなりません。
メンバーで相談しながらなんとか定款案を作り、理事・監事をきめ、登記に臨むことになりました。私たちは自ら定款を作成しましたが、弁護士、司法書士など専門家にチェックをお願いすると安心かもしれません。これ以外に、法人化後はメンバーから会費を集めることにしました。元々会費を取らずに運営していたのですが、帰属意識や法人を続けていく、という意思を高める狙いもあり、合議で決定しました。そして、ロゼッタに長期的に関わっているメンバーが設立時社員*2となり、共同で法人のオーナーとなることも決めました。
公証役場での定款認証
定款ができたらすぐに法務局で登記できるわけではなく、法人の住所を置く都道府県内にある公証役場で「定款認証」をしてもらう必要があります。私の場合、校正役場にまず電話をし、指示に従いメールで定款案と記入済みの「実質的支配者となるべき者の申告書」(必須書類)を送りました。その後公証人から全員分の印鑑証明の画像を送るように依頼を受け、準備して送りました。これは定款内に記載する設立時社員の住所が、印鑑証明と一字一句同じである必要があるためです。平日に仕事がありなかなか役所に行けないメンバーもいるため、少し時間がかかる作業でした。
その後、公証人の方から電話があり、定款について数箇所修正の指示を受け、内容を修正したうえで、再度確認いただいた後OKをもらい、公証人の指示にしたがって公証役場の予約を取りました。私の利用した公証役場の場合、必要書類のリストや、委任状のテンプレートなどもすべてメールで提供してくださいました。私たちは紙の定款による認証を選んだので、公証役場で認証してもらう必要がありますが、テレビ電話を通じた、電子認証も可能です。利用するには設立時社員全員がマイナンバーカードを持っている必要があります。また、年度末である3月に定款認証を済ませたかったのですが、公証役場が大変混雑しており予約がとれず、結局年度明けの4月に予約することになりました。
今後の流れ
新年度の4/1に定款認証を行い、その後登記を行う予定です。登記が終わった後は、理事会を開き、理事報酬・監事報酬の決定(事前におおまかに話し合っています)、社会保険への加入など、フリーランスの時にはなかった事務作業が発生します。経理事務に備え、日商簿記3級を取得しましたが、今後もあると便利そうな資格・検定を取得する予定です。新年度には、実際に登記して法人を立ち上げ、運営を始める部分を紹介するパート2の記事をお届けしたいと思います。
*一般社団法人の社員とは、従業員のことではなく、法人の運営者(株式会社でいう株主)のことを指します。設立時社員とは、文字通り設立時の社員です。
(注意)本記事で紹介している法人の設立方法は2025年3月時点の情報です。現行の法律に変更がないか、各自の責任で確認の上、ご参考になさってください。
【ロゼッタ】
京都・関西を拠点とし、音楽表現を中心としたアートコレクティブで、音楽表現、音楽鑑賞の両面に対し、新たな観点をもたらすことを目標に結成されました。毎年度ゲストコンポーザーを招き、委嘱作品の演奏とともに、公募を行い、世界各国のあらたな作品を世に送り出しています。
https://rosetta-music.com/