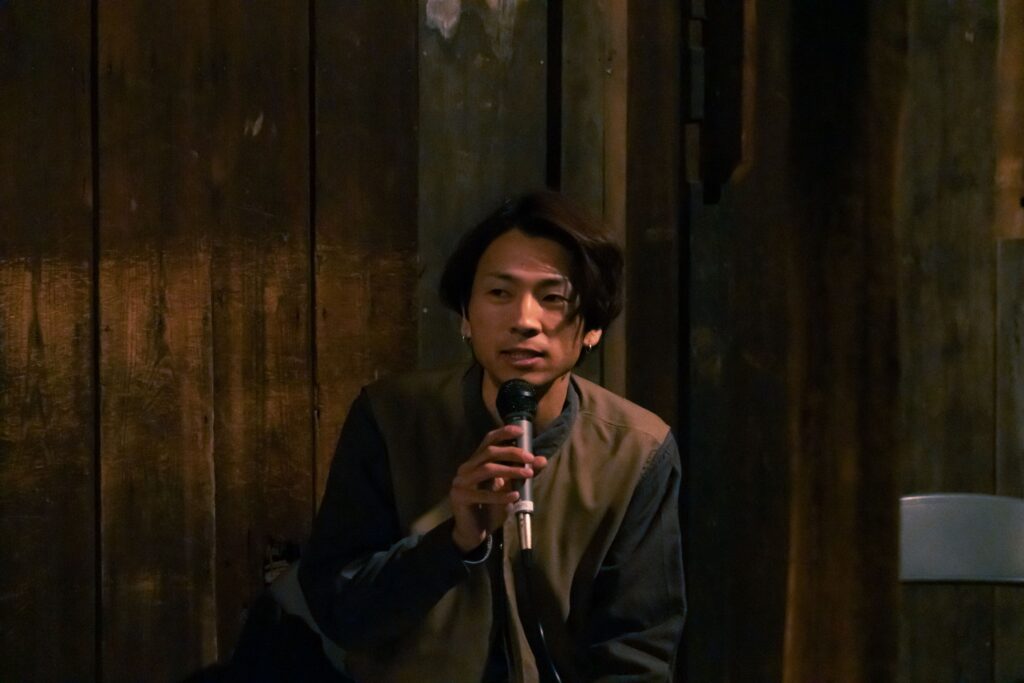Kyoto Art Mates
京都で美術に携わる大学生や卒業してまもない若手を対象にしたゲストトーク&意見交換会。ゲストには作品制作にとどまらず多岐にわたって活動を展開してきた経験豊富なアーティストを招き、美術に関わる多様なキャリアや選択肢についてお話を伺います。作家活動に限らない美術を取り巻くさまざまな可能性を探りながら、参加者が抱える悩みや課題を互いに共有し、解決策や新たな視点を見つける場として提供されます。
今回は、レクチャーの後、ゲストの松井沙都子さんと企画者4名によるディスカッションが開かれました。
>>>「Kyoto Art Mates:京都で美術ってどう続けられる?」 【レクチャー】へ
ディスカッション:トピック一覧
・制作のモチベーションについて
・作品の保管について
・企業の支援について
・作品を売ることについて
「Kyoto Art Mates:京都で美術ってどう続けられる?」
【ディスカッション】
日時|2025年2月23日(日・祝)
会場|TAKI/焚(京都市中京区)
登壇者|
松井沙都子(アーティスト)
北村侑紀佳(アーティスト)
佐藤星那(アートディレクター)
山﨑愛彦(アーティスト)
平野成悟(キュレーター・アーティスト)

佐藤星那 撮影:沢田朔
=制作のモチベーションについて
佐藤:作品制作と展示のヒントについてお伺いしたいです。大学卒業後、アウトプットの機会は意識的に設けるようにしていたのでしょうか。
松井:私の場合、卒展を見に来られたギャラリーにポートフォリオを持ち込んで、半企画という形で個展をさせてもらったのが最初の発表の機会でした。そのあと個展やグループ展の話が続いて、年に一回くらいのペースでは必ず発表できていました。運が良かったと思います。でもこれまで相談を受けてきた中では、発表の機会がぷつっと切れてしまって、一体どうやって活動していったらいいんだろうと悩んでいる人も多かったです。卒展で良い評価をもらった人が引く手あまたになることもあるとは思いますが、そういう人ばかりでもないので、何が決め手になるかは一概には言えません。私自身は、自分で動いたことに加えて、シェアスタジオにいたことも良かったのかなと思います。
佐藤:制作や発表の頻度を自分で決めなければならなくなったときに、間延びするといいますか、気持ちが制作に向かなくなったりすることなどの変化はありましたか?
松井:大学で締切りを作ってもらっている訳じゃないのに、どうやって続けていくかということですよね。山﨑さんはどう維持されていますか?いま大学に所属されていると思うんですけど。
山﨑:これまで制作のモチベーションと発表のバランスをどのようにとるか大きく悩んだことはありませんでしたが、最近は発表の機会が増えてきて、どうやって作品を作ったらいいかがわからなくなってきています。博士課程一年目ということもあって文章を書く機会が多く、インプットの時間もかなり取らないといけなかったりして…。制作だけに重心を置くことが難しい状況になってきて、じゃあ制作とそれ以外のことをどうやって並行して続けていくかという問題に早速ぶつかっています。
松井:わかります、そうですよね。予定の方が先に来て自分が追いつかない逆転現象というか…。
山﨑:今はとにかく全然関係ないことで手を動かしながら、ちょっと別の制作をしています。そうしているうちにいつか本筋の方に戻って来られるんじゃないかと。今は迷走しているところですね。
松井:私も一時期、作家の友人と集まって手芸サークルのようなことをやっていたことがありました。私の場合はひたすらポーチなどを作り続ける活動でしたが、やっぱり創作がうまくいかない時の捌け口が必要なときもあるなあと思っています。だってずっと上り調子というわけではないじゃないですか。停滞したりわからなくなったり、今までのことが全部無駄な気がしてくる瞬間があったりして。モチベーションの維持というよりも、制作のアップダウンにどのように実際の活動を寄り添わせていくかということの方が難しい感じがします。
=仕事について
山﨑:私から質問です。今日来てくださっている方々のなかには既に文化事業に関する職に就いている方もいれば、学生として漠然とした不安を共有しに来られた方もいると思います。私はちょっと前まで成安造形大学で助手として勤めていたんですが、美術にまつわる仕事といわれて私がパッと思い浮かぶものだと、私が勤めていたような大学の助手だったり事務職員や教員、あるいはアートフェアや芸術祭といったアートイベント関連の仕事に期間限定で就くような方法もあるかと思います。ただ、今後そういった仕事や文化事業に携わりたい場合にどんなアクションをしていったらいいのかは私も模索していて、松井さんならどんなご提案をされるのだろうかと気になっています。
松井:どうでしょう。そういうことをよく聞かれますか?
山﨑:「どうやって助手になったんですか」とか、「なんで京都に来たんですか」みたいな質問がよくあるんですが、私の場合は人に恵まれたとしか言えることがないというか…。
松井:平野さんはいろいろ仕事されていると思いますが、どうやって見つけられているんですか?
平野:僕も人に恵まれているとしか……。(笑) ただ、恥ずかしい話なんですけど、SNSで「仕事をください」と正直に言っていましたね。前職を退くことになったものの、次の働き口も見つからないままだったので、藁にをもすがる思いというか。生活費とか活動費をアルバイトだけで捻出するとなるとだいぶきつい状態で、それでも自分がやっている活動に重なるような仕事を探していたとき、以前に一度お仕事させていただいたところから人手が足りなくなったので働いてみないかと誘っていただけたんです。でも自分のようなケースはすごく恵まれているという自覚はあるので、決して「そういうものです」とは言えません。ただ、強いていうなら僕は展覧会を作るという活動をしていたので、おそらくそこを買ってもらえたのではないかと思っています。例えば写真作品を作る作家さんが他の人の展覧会にアーカイブ撮影のカメラマンとして携わることがありますし、他にも作家がインストーラーやデザイナーとしてメインにしている活動のノウハウを活かして生計の足しにしているケースもよく目にします。そして自分もその類になると思います。「作品で食っていかなきゃ」というよりは、それに付随するスキルでどう仕事を作れるかということを一つ考えてみてもいいのかなと、個人的には思います。
松井:わかります。売り込みって、案外やっている人は多いと思います。私も春から非常勤講師を何年かぶりに再開しますが、「非常勤講師をめっちゃやりたいんです」、「教職志望なんです」と、いろんな人に言いまくりました。するとちゃんと然るべき人に届いたんです。言わなかったら誰も自分が仕事を求めているなんて思わないので、口にすることは本当に大事だと思いました。
平野:逆に忙しいと思われてしまって声をかけられない、というパターンもあります。
松井:そうなんですよね。だからちゃんと困ったら人に伝えるということを大事にしよう、と言いたいです。やっぱり一人で抱えないのが大事なのではないでしょうか。あとは、文化芸術系の仕事情報が集まるウェブサイトもあるので、そこで調べてみるのも良いと思います。公募されている仕事も案外たくさんありますよ。例えば大学の教員公募に特化したサイトもあって、そこで公募されている仕事に正規のルートでエントリーすることもできます。選択肢はいろいろです。
山﨑:大学教員の求人だと応募時にポートフォリオや研究業績書といった書類を一緒に出しますよね。その応募で不採用になっても、応募書類を見てくださった方が非常講師に呼んでくれたりとか、ゲスト講師で来てくれませんかという依頼を個別でくれる場合もあるらしいです。なので、気になってる求人にはガンガン応募しちゃえばいいのでは、と個人的には思っています。
松井:選考にあたるのも人ですから、書類で名前を見て「こういう人がいるんだな」と知る機会にはなると思いますよ。聞くところによると公募展でも、毎年この人出してるな、とか覚えてくれている審査員もいるらしいです。いろいろ動いてみると、どこにチャンスがあるかわかりません。
平野:たしかに。そう思うと、自分がやってることを他人から見えるようにしたうえで「何々に関心があります」みたいなことを言っておくことで、もしかすると後々に同じ趣向をもった人からの声かけもあるかもしれない。
松井:公募とか助成の応募書類を書くのが苦手で、「何を書けばいいのかわからない」とか、「自分の作品や取組について書いてくださいとか言われても困る」と感じる人も多いと思いますが、そういった書類は書けば書くほど上手くなるし、そのうち適切なキーワードが見つかって、いろんな人に一発で伝わるような文章が書けるようになっていきます。やっぱりアウトプットすることはすごく大事。公募に応募することは人からジャッジをされるようで嫌かもしれませんが、公募では自分がなにをやっている人なのかをその道のプロに伝えることができて、そのうえ自分の作品や活動がどういうものなのかを見抜いてもらえる可能性もある。さらにうまくいけば新たな人脈につながる可能性もあったりと、いいことばかりだと思います。
佐藤:種を撒いていかないとっていうことですよね。
松井:そうですね。
=作品の保管について
佐藤:話が変わりますが、これまで制作した作品の在庫はどうされているのでしょうか。
北村:私も聞きたいです。私も含め若手アーティストって大きい作品を作りたい傾向があると思います。とはいえ大きい作品はあまり売れませんよね。やっぱり小さい作品の方が売れるし、在庫としても管理しやすい。大きい作品に限りませんが、作品の保管の仕方なんて誰にも習っていないからいまだに自己流でやっています。なので、お話をうかがえたら嬉しいです。
松井:北村さんは卒業するときにどうされるんですか?
北村:いまちょうど大学に置いてある作品を一箇所に集めているところで、今度トラックを借りて一旦全部持って帰ろうかなと思っています。
松井:実家に、ですか?
北村:そうです。それで保管できない作品は破棄していくことになるかな、と思っています。
松井:そうですよね。皆さんは捨てていますか?
山﨑:私は全然捨てていません。倉庫が広くなっていくばかりです。
松井:置き場所が拡張していってるんですね……。
山﨑:実家が北海道なので、京都に移住してから作ったものを送るに送れず、倉庫を借りています。ペインティングは売れやすい傾向があるので、それほど切羽詰まっているわけではないんですが…。でもいつかコレクターの方から大きな作品を返したいと言われないとも限らないし、破棄してしまうかもしれない。そうなるとあまりいい状況ではないので、もう少し確実に管理をしていきたいところです。
平野:逆に言うとそういうふうに管理に困るのがわかっていて、あえて大きい作品を作らない傾向もあるらしいですね。だんだん学生の作品が小さくなっていっているという話を教授陣から聞きます。
松井:そうですね。でも大学のアトリエって広いから作品も小さく見えるけど、実家に置いてみると50号とかで部屋がパンパンになるじゃないですか。空間によって作品の規模感は全然違うから、作品のサイズ感というのは小さいものを作るから駄目だとか、絶対的な数値の話じゃなくて、相対的なものだと思います。だって展覧会をするときのインストールにしても、空間によって小さく見えたり大きく見えたりするわけじゃないですか。だから大学を出て作品が小さくなるのは自然なことだと思うんですけどね。
ちなみに私の作品は、大きいんです。でも絵画みたいな一点ものという感覚があまりないので、一度展示をしたらその場で作品をバラして、舞台の大道具のようにパーツごとに保管するという風にしています。それも全部を保管しているわけではなく、作品が展覧会場で成立する状態をまた作れたら良いという発想で、次の展示の時に再制作できるものは捨てるなどして、部分的に保管をしています。絵画のような平面は比較的管理がしやすいと思いますが、とはいえ場所がなくなってきたら、やっぱり捨てざるを得ないですよね。そうなると、大事な作品も粗大ゴミになってしまう。産業廃棄物として処分しないといけないし、悲しい……。でも置き場所に制限がある以上、処分しないといけない作品は、淘汰されていると思わざるを得ないですよね。
平野:すごく重要な自覚だと思いますね。たとえ美術史的に重要な作品だったとしても、然るべきところになければ、それは場所をとるものでしかなくて。
松井:いま、価値がある作品でも美術館が引き取ってくれない状況になってきていると聞きます。寄贈したいと申し出ても、ストレージがいっぱいで断られたり、存命作家の作品は引き取れないと言われたり…。美術館すら作品を残してくれないのに誰が残してくれるのか、と思いませんか。ましてや自分で破棄するタイミングを見極めるなんてどうしたらいいのかな、と思いますよね。どう判断してます?卒業制作作品をいつ捨てるか、とか。
北村:私は学部の卒業制作が150号の絵画作品で、いま実家に置いてあるんですけど、壁のようになっていて邪魔だと感じています。でもコレクターの方から卒業制作作品を見たいと連絡をいただくこともあり、となると捨てるのもちょっとな……、という思いもあります。特に私の作品は描写が細かいので、アーカイブとして写真に残しきれない部分があり……。だからずっと置いているんですけど、それによって制作できない壁面が一つ生まれてると思うと、良いのか悪いのか、という気はしています。
松井:確かにそうですよね。作品は役目を終えたと感じたときに捨てるというのが良いのかもしれません。私は複数あった卒業制作作品の多くは早くに廃棄してしまったんですが、一部とっておいた作品はありました。でもそれも卒業して15年後くらいに、借りていた倉庫が訳あってなくなることになったときに、捨てました。その作品は大事だったもので、制作の経緯もよく覚えてたし、いつかまた展示するんじゃないかと思っていましたが、廃棄の選択に迫られた時に、もうこの作品は今の自分の作品の流れと全然違うので、まったく参考にならないと思って、廃棄を決めました。つまり作家としてのキャリアの一部ではなく、卒業制作以外の何ものでもない、と思ったときに捨てる決心がつきました。置いておく場所がなまじあったら捨てられなかったかもしれません。今となっては、捨てられて良かったなと思っています。
山﨑:ストレージに関する補助制度がもっとあったら残ってたかもしれないですね……。
松井:そうですね、ただ残っていても無駄なものを残していたかもしれないと思うと、ストレージの支援があるのもどうなのかなと思えてきました。今は困っているけど、将来的には作品がいらなくなって、不良在庫の山が倉庫に蓄積されていき、最悪、誰も引き取り手がない・取りに来ないみたいなことになりかねないのではと……。
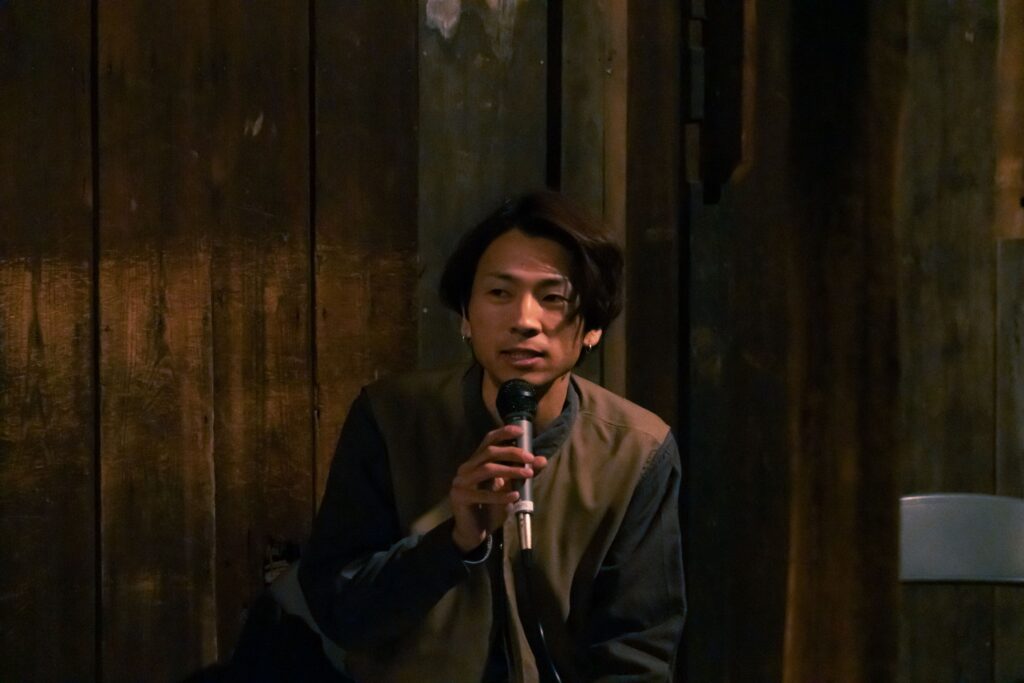
平野成悟 撮影:沢田朔
=企業の支援について
「個人として制作活動をしているわけではなく、印刷会社でできる文化芸術への貢献、作家への支援などの取り組みを考えています。なにか今後に繋がる考えや知識を勉強したく参加します。」
山﨑:事前にいただいていた質問を取り上げようと思います。今日は自身が制作活動をしているわけではないが、印刷会社としてできる文化芸術への貢献や作家への支援などの取組を考えていらっしゃるという方にも参加いただいているようなので、今後何かにつながる考えであったり知識の共有をできればと思います。京都にはHAPS(東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス)であったりKACCO(京都市文化芸術総合相談窓口)などの文化事業や個人・団体による活動を支援する機関がありますが、さらに企業や個人単位でも支援の目線を持ってくださっている方々がいるようです。そういった美術の仕事をしているわけではないが、これから関わっていこうと考えていてくださる方々に向けて、我々としては何が言えるでしょうか。
松井:質問としては企業さんの文化芸術支援についてですよね。すでにいろいろあるのではないでしょうか。企業メセナという形で公に取り組まれているところもあるでしょうし、自社の技術やノウハウを個人向けに提供する、もしくは資金面で全面的に支援するような取組をされているところもあったりするはずです。きっと、支援したいがどうすればいいか、何が必要とされているのかわからない、と悩まれていると思うのですが、何ができるかは……どうでしょう。御社になにができて、その手段をもってどのような形で文化芸術を支援したいかによる、という感じではないでしょうか。
平野:支援するにあたって自社の強みが明確に打ち出されていたら良いと思います。HAPSだったり、京都のマッチングをしてくれるところがキャッチしてくれるので。
松井:京都芸術センターを拠点にしている「器」が企業さんとのマッチングのご相談に乗っていますね。「器」はアートとビジネスの新しい関わり方を模索していく取組だと聞いています。芸術センターの中にテナントとして企業さんを入れたり、企業さんとアーティストとのマッチングの相談に乗ってくれたりもするようです。
平野:京都芸術センターを拠点にしている「器」が企業さんとのマッチングのご相談に乗っていますね。「器」はアートとビジネスの新しい関わり方を模索していく取組だと聞いています。芸術センターの中にテナントとして企業さんを入れたり、企業さんとアーティストとのマッチングの相談に乗ってくれたりもするようです。

左から:山﨑愛彦、北村侑紀佳、松井沙都子 撮影:沢田朔
=作品を売ることについて
松井:作品を売ることについてちょっと聞いてみてもいいですか?皆さんは自分の作品を売りたいですか?
北村:私は新しい制作のためにも在庫を減らしてお金も得るという気持ちで売っている部分が大きいですね。その中でちょっと困っているのは、作品のなかでもニーズの多い作品とそうではない作品があることで、たまに前者を作りたくないときもあったりするんです。売りやすくて売るために作るような作品と、自分がやりたいような作品が、乖離するときがある。そのあたりは割り切れない部分としてモヤモヤしているところではありますね。売ることに対して否定的なスタンスではありませんが、自分の制作との兼ね合いとしては悩みどころです。
松井:売れやすい作品には、どういう傾向がありますか?
北村:私の作品でいうと手数が多いというか、一目で制作の労力がわかるようなものがやっぱり売れやすいです。
松井:そうかも。作業量がわかりやすいと、買う側からするとコスパが良く感じられそうですよね。
北村:評価がそれに偏るところもあって、それがすごくジレンマです。
松井:なるほど。山崎さんの場合は、どんな作品が売れやすいですか?
山﨑:私にはどういった作品が売れやすいのかはわからないのですが、私の作品はいろんな国や土地に分散すればするほどコンセプトが機能する作品なので、作品同士のネットワークが国外にも広まって、地球上をメロンの網の目のように覆い尽くせたらいいなと考えています。なので売れれば売れるほど嬉しいですが、特に傾向がわかっているわけではないんですよね。
松井:急に思いもよらなかった作品が、ポンと売れたりする感じなんですか?
山﨑:そういう時もあります。当てが外れると痛い目を見るので、あんまり期待せずに発表していますが、意外に売れて嬉しかったこともあれば、案外売れなかったこともあります。
松井:あと自分の作品が売れていない一方で、一緒に展示した人はめっちゃ売れていたりすることもありますよね。
平野:さて、いろいろと話題はつきませんが、そろそろお時間が近づいてきました。ここからは場をひらいて参加者のみなさんとも自由にお話ができればと思います。改めまして松井さん、素晴らしいお話をありがとうございました。

撮影:沢田朔
松井沙都⼦ MATSUI Satoko (アーティスト)
2004年3⽉ 京都市⽴芸術⼤学美術学部美術科油画専攻 卒業
2006年3⽉ 京都市⽴芸術⼤学⼤学院美術研究科修⼠課程絵画専攻油画 修了
2017年3⽉ 博⼠(美術)(京都市⽴芸術⼤学)
不在の空間を⽣み出す構造について研究し、インスタレーションを中⼼に作品を展開している。近年は〈現代の⽇本の家〉や絵画の〈フレーム〉をモチーフとした抽象的な作品の制作に取り組む。修⼠課程終了後、京都市右京区太秦にシェアスタジオ「ウズイチスタジオ」を⽴ち上げ、14 年に渡りスタジオ運営と⾃主企画を⾏う。現在は同地域の「⼭ノ外スタジオ」に拠点を移し、オープンスタジオなどの企画にも携わっている。
北村侑紀佳 Yukika Kitamura (アーティスト)
2000年 滋賀県生まれ
2023年 成安造形大学 芸術学部 芸術学科 美術領域 洋画コース 卒業
現在、嵯峨美術大学 大学院 芸術研究科 在籍中
不在の中で誰かがそこに居たという痕跡や気配が個々人のアイデンティティを超えてただ「生」を示していることに注目し、その存在に触れるための作品を制作。
佐藤星那 Seina Satou (アートディレクター)
2002年 宮城県生まれ。
2024年 京都芸術大学 芸術学部 情報デザイン学科 ビジュアルコミュニケーションデザインコース 在籍中
日常の中に展示空間を立ち上げていく、Explore Kyoto という活動(現在3回目)を行っている。
平野成悟 Seigo Hirano (キュレーター・アーティスト)
1996年 大阪府生まれ
2019年京都精華大学 芸術学部 造形学科 洋画コース 卒業
2022 年 京都市立芸術大学 大学院 美術研究科修士課程 油画専攻修了
在学中より、自身の作品制作・発表 と平行して展覧会のキュレーションを手掛けている。
山﨑愛彦 Yoshihiko Yamazaki (アーティスト)
1994年 北海道生まれ
2016年 札幌大谷大学 芸術学部 美術学科 造形表現領域 絵画コース油彩分野 卒業
2020年 北海道教育大学 大学院 教育学研究科 教科教育専攻 美術専修 (油彩画) 修了
現在、京都市立芸術大学大学院 美術研究科 博士後期課程 版画領域 在籍中
近年は無名の個人がSNSでシェアする画像(綺麗な空や旅行先の風景や食事など)を、寿命以上に永く残せるような絵画として描く試みを行っている。
「Kyoto Art Mates:京都で美術ってどう続けられる?」
コーディネート|北村侑紀佳、佐藤星那、平野成悟、山﨑愛彦
主催|京都市、京都市文化芸術総合相談窓口(KACCO)
協力|一般社団法人HAPS