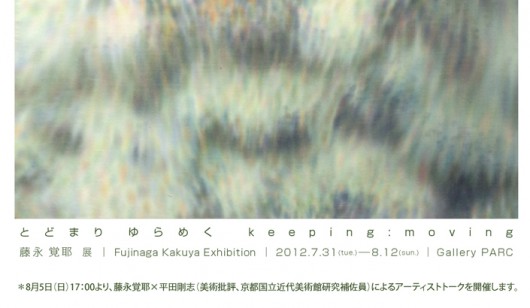藤永覚耶(ふじなが・かくや / 滋賀・1983~)は、2006年に京都嵯峨芸術大学版画分野を卒業の後、2008年に愛知県立芸術大学 大学院美術研究科油画専攻を修了以降、これまでおもに愛知を中心に定期的な発表を続けています。本展は2011年から再び活動の舞台を京都に移した藤永にとって、はじめての個展となります。
藤永作品の特徴は、まずモチーフ(近年では森や植物)を写真により撮影し、その図像をもとに、布地にアルコール染料インクを用いて点描し、最後に溶剤でその図像を溶かすというプロセスにあります。それは、一見すると「写真をボカす=写真の持つリアリティを鈍くしていく」行為と呼べるものであり、作品の画面にはどこか不明瞭で抽象的なイメージが出現しています。しかし、藤永は「写真のピントが鮮明に合った箇所よりも、ボケやブレにリアリティを感じる。それは再現的なリアリティではなく、個人の先入観や価値観をぬぐい去った等価な世界に立ち戻るような真実味を持った感覚である」として、そのボケたイメージにリアルではなく「真実味」を見いだすと言います。
私たちの目に見える世界は、常に時間が流れ、その時々の光量や目の焦点によって、色・形といった知覚・認識すら不確かな「うつろい」の中にあるといえます。その一瞬を切り取り、すべてに焦点があった写真は、本来は知覚し得なかった世界の「イメージ」であるとともに、私たちはそのイメージから擬似的なリアリティを再現・変換しているといえるのではないでしょうか。
等価の点(情報)の集合である写真を、目と手によって点(図)に置き換え、溶かすことであらわれたボケた図像は、写真の持つリアリティやドキュメント性、作家の意図や意識、見る者の主観や想像など、私たちの知覚や認識を超えた世界の「ありのままの姿」を留めているのかもしれません。藤永は2009年より、その展示方法にも展開を試みています。布地のまま空間に吊り下げられた作品は、透過光や風の影響を受けてより不定形にゆらぎ、その一様でない姿を体験させるものとして取り組まれてきました。
これまでおもに愛知を中心に活動してきた藤永にとって、京都での初の個展となる本展では、平面作品を中心に構成し、その魅力を紹介いたします。また会期の8月5日(日)には、平田剛志(美術批評、京都国立近代美術館研究補佐員)氏を聞き手に迎えたアーティストトークを開催し、自作解説とともに、今後の作品展開についてのお話をうかがいます。
展覧会について
写真のピントが鮮明に合った箇所よりも、ボケやブレにリアリティを感じる。それは再現的なリアリティではなく、個人の先入観や価値観をぬぐい去った等価な世界に立ち戻るような真実味を持った感覚である。 そこには時間や光の焦点など、本来形を一定に保っていない世界の状態の一端が現れているように思う。そして、そこに個を離れた大きな世界の断片を感じ取ることができる。
しかし、それと同時に、様々な基準の中で日常を営む自分がいて、そこに到達できないことを思い知らされる。そのような、日常を営む個の世界と、個を離れた非日常で等価な世界との狭間で揺れ動くものを、平面イメージとして空間の中でいかに表現できるかということを考え、制作を続けている。 僕の制作は、写真から得たイメージを、自分の手を通して綿布の上でインクの点に置き換えてゆく。そして、一度固定されたそれらの点は、溶かされることで、もう一度動き、混ざり合い、動きをとめる。そのように作られたイメージを、しばしの間、作品というかたちで固定する。
今回の展示では、壁面展示の平面作品に加え、ギャラリーパルクの南から入る自然光を取り入れた矩形の床設置の作品を展示する。
時間や天候によって変わる自然光の状態によって作品の見え方は変化し、その色彩は、絶対的なものではなく、空間と呼応するような相対的なものとなる。
展示を通して、ただそこにあるイメージを、空っぽの状態で見て頂ければ幸いです。
アーティストトーク:8月5日(日) 17:00?