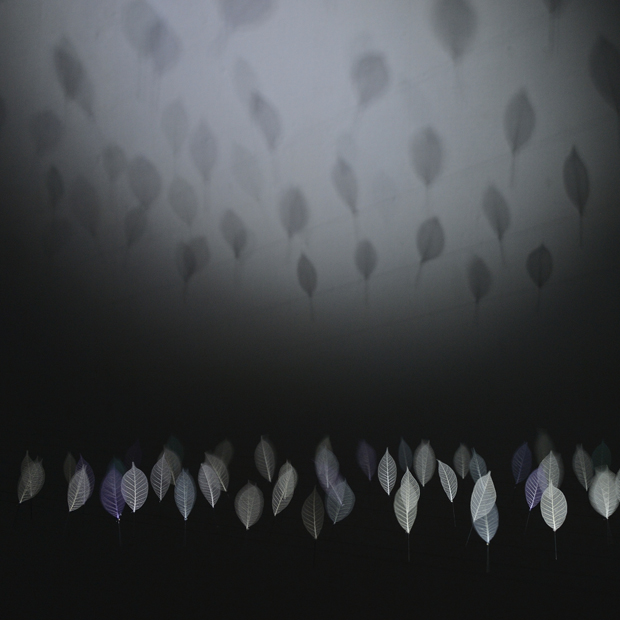
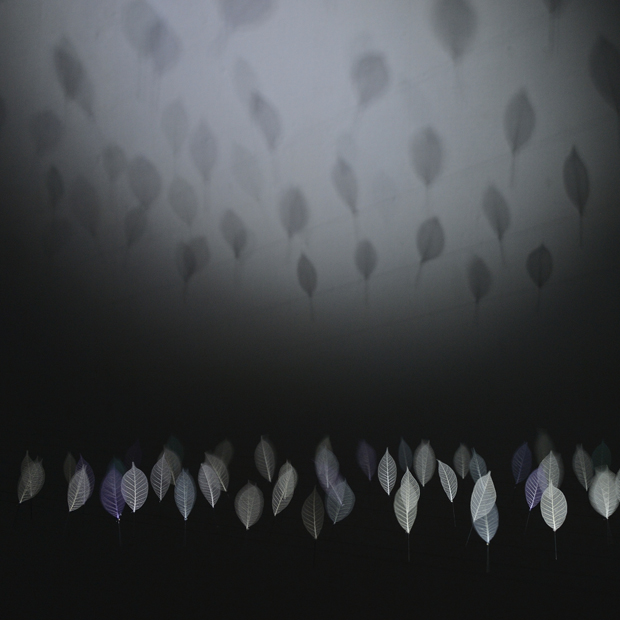
「インスタレーション」という言葉
加須屋:まず最初に少し「インスタレーション」という言葉のこととか、これまでどういう経緯で作品が発表されてきたか、ということを簡単にお話したいと思います。
「インスタレーション(installation)」という言葉は、install(=設置する、取り付ける)という動詞の名詞形です。現在は、仮設の組み合わせによって空間全体を構成した展示、場所と結びついたサイト・スペシフィックな作品、あるいは展示空間全体を体験するような作品のことだと理解されています。これは美術における一つのジャンル、または展示形式として、日本では80年代から90年代にかけて一般的になってきた呼称です。
戦後、芸術作品のさまざまな新たなかたちが提案され、取り組まれてきました。だいたい50年代から60年代にかけて、作品の形式の多様化に伴って、「アースワーク」や「ランド・アート」などと呼ばれる、画廊を飛び出して屋外で展示する作品形態が出てきました。それらは一回きりのことも、永久に残る場合もありますが、作品の形式として「仮設」というものが現れてきました。よく「ランド・アート」の例に挙げられるロバート・スミッソンの《螺旋形の突堤》(1970)も、もとは永久に展示されることを想定して作られたものではありませんでした。例えばクリストの《ランニング・フェンス》(1976)などは、全体の景色の中にこの時だけ存在するもので、その後は写真や映像でしか見ることが出来ません。
また、例えば60年代より世界各地で盛んに行われる「ハプニング」や、「パフォーマンス」など何かを鑑賞する状態をその場所全体に拡げ、それを一時的な展示空間とするものも出てきました。こういった、様々な作品形態が生まれてくる中、徐々にいわゆる古典的な絵画や彫刻を作って展示場に置くということだけでなく、例えば油彩の作品であっても展示する状態によって見え方が変わるということ、あるいは空間全体をどういうふうに演出していくかということに、作家の側でも意識がより強く向けられるようになってきました。また、都市空間の中に公共空間に作品を建物と共に設置する「パブリックアート」の動きも盛んになりました。このようにして、屋外での展示やパフォーマンス、またビデオやメディアアートなど様々なメディアを用いた作品が増え、従来の展示とは異なる形式が求められ、意識されるようになるにつれ、それらを表すために「インスタレーション」という言葉が新たな意味を伴って使われるようになってきたわけです。
次に、私自身が美術館で手掛けてきた展覧会の出品作品のうち、「インスタレーション」つまり作家自身が空間全体を構成する作品についてお話しします。例えば映像のインスタレーション、部屋を作ってその中にプロジェクター、スクリーン、スピーカーなどを設置して空間全体を味わうという作品の場合は、とりわけ空間の使い方が重要になりますので、設置自体が展示体験を左右するものとして非常に気を使いながら行われていました。また、以前に別の場所で展示を行った作品を持ってくる場合には、作品の一部を輸送して持ち込み、それを用いて再制作するという形を取りました。これは再現が可能なタイプのインスタレーション作品、ということになります。そして、展示空間全体を作品とするものの例として、須田悦弘さんの木彫作品を挙げたいと思います。作品のサイズは「サイズ可変」と書かれており、木彫そのものだけでなく、展示空間全体が自分の作品であるということを示しています。彼は、かなり早い段階からそういったことを明確に意識しておられ、その点で「インスタレーションの作家」と言えるのではないでしょうか。それから、塩田千春さんの《大陸を越えて》(2008)という作品は、靴を集めて、それぞれ人々の思い出を書いていただき、展示の場で赤い毛糸を繋いでいって作ったインスタレーション作品でした。展示が終わったら全部撤去してしまいました。この場所でしか出来ないわけではないですが、やはりこの場所に合わせた形では他の場所では出来ない、と意味では「サイト・スペシフィック」と言えます。
それでは、美術館ではない場所での「インスタレーション」について、原さんにバトンタッチしたいと思います。
展示空間と鑑賞者
原:
私からはまず、YOSHITOMO NARA + graf 「A to Z」についてお話ししたいと思います。これは私自身が企画というよりプロジェクトに実行委員の一人として関わったもので、キュレーション自体は奈良美智さん自身がされたのですが、一つの事例としてお話しします。これはもともと古い酒蔵だった煉瓦倉庫を使ったこの建物全体がインスタレーションと言えるものです。先程、加須屋さんがおっしゃっていた「インスタレーション」の定義というもの中に「サイト・スペシフィック」や展示体験などいろいろなお話がありましたが、もう一つキーワードを出すとすると、出来事、あるいは事象の連鎖のようなものが、たびたび「インスタレーション」というものの中には出てくるということです。そこが彫刻などとは若干違うところなのかな、と思っています。
特にこの「A to Z」というタイトルですが、1から10まで、と似たようなもので、いろいろなことが全てこの中に連鎖として繋がっている、というイメージがあります。ロンドンなどで「A to Z」という地図を買ったことがある方はなんとなくおわかりになるのではないでしょうか。入り口を入って行くところから、ある種のワンダーランドが始まるような感覚です。そこにはAからZまでの小屋が作られていて、さまざまなアーティストたちが参加していたのですが、ここで出会う様々なものは、人によっては見る場所が異なったりしますし、作家自身の意図とそれを見る人たちの蓄積してきた記憶を重ねあわせながら、様々な解釈の仕方が可能です。それぞれの小屋で出会うもの、私たちがそこに辿りつくまでの間に考えること。出来事や事象の連鎖に加えて、身体を介在させている移動のなかでいろいろ体験するものというのも、インスタレーションの特徴かもしれません。
松井智惠さんは非常に素晴らしいインスタレーションをお作りになるアーティストの一人だと思います。例えば信濃橋画廊で作られた作品を例に挙げますが、それは、地下空間から入っては出て、入っては出てというような瞬間を繰り返しながら空間のなかを移動していく本人の映像があって、それがインスタレーションの一部にもなっているものです。彼女の作品は、ある場所のなかで、いろいろなその空間の見方、思考の仕方や場所に対する意識をもう一度あらためて私たちに提示してくれます。
さて「六甲ミーツ・アート」という展覧会が9月14日からはじまりました。今年で4回目になるのですけれど、六甲山頂にあるいくつかの施設で行われるもので、ほとんどが屋外での展示です。毎年、いわゆる屋外彫刻とインスタレーションと考えられる作品が混在しています。
その中に、ロイヤルアイシングというお砂糖を使った素材で壁画を描いた、佐々木愛さんの《ふたたびの森》という作品があるのですが、これは「インスタレーション」と考えて良いでしょうか。この「インスタレーション」という言葉は非常に便利でもあり、厄介でもある、と私は常に思っています。つまり、壁画であってもそう言える場合と、壁画というくくりだけに留まってしまう場合があるのかな、ということなんですが。
加須屋:
そうですね、使われている素材がアイシングなので、永久保存できないという意味では仮設で、インスタレーション的なのかなとも思います。空間全体に対する意識が非常に強いという意味でも。他の場所に持っていけば同じプランではなかったでしょう。そういう意識がこのごろ高まってきている気がします。この作品の場合はホテルという、もともと意味のある場所に展示されていますが、そのことを意識しながら作っていく傾向が強くなっているということでしょうか。
原:置かれている調度品や、天窓のステンドグラスなど、その空間をつくりだす要素自体にも特別な部分もあるし、それと呼応させながら作品が成り立ってくることもありますね。

加須屋:六甲には大西康明さんの作品も展示されています。六甲オルゴールミュージアムの敷地内に展示された《六甲白景1》についてお聞きしたいと思います。今回、京都芸術センターで展示されている尿素の結晶を用いたものとは違い、以前から手がけられている接着剤の作品に近い…けれども、ちょっとタイプが違うように思えます。
大西:そうですね、初めて外で展示した作品なので。外と言うか、元はバンガローだった場所で、その残った基礎下の空間で雨はしのげる半屋外のようなところです。台風で少し壊れてしまったようなのですが。
加須屋:
復旧が必要、ということですね。そういうリスクを含む半屋外の展示だと思うんですけれど、何かこの場所でこれを、という決め手があったんですか?
大西:
六甲山で展示するにあたって、大自然のなかでは自分の作品を置けないと思っていて、簡単にいえば本当に生えてる木に直接接着剤をかけて作品をつくるのはちょっと無理。となると、雨風を防げるところに展示した方が良い。そこで、なんとなく人の気配が残っている場所、つまり、六甲山を非日常だと思って訪れたお客が一晩泊まったこの場所に、何か作ってみたいと感じてここを選びました。(その他、《六甲白景2》も出品)
加須屋:
ではそろそろ事例報告はこの辺にしまして、ちょっと視点を変えて、鞍田先生に「空間」をキーワードに話をお聞きしたいと思います。
空間としての「インスタレーション」
鞍田:
インスタレーションを体験するという視点から、少し話をしたいと思います。今日この話題を出そうと思ったのは、自分自身が今回の展示を観た時に抱いた印象からです。大西さん、松澤さんの両方とも素晴らしい作品で、ものすごく心地の良い空間だったんですね。そして、特に大西さんの展示では、まわりから観るのではなく、あの樹氷のような隙間の中に入っていって、そこから外を眺めてみたいと思いました。インスタレーションとはアート作品であり、鑑賞する対象ではあるのですが、同時に、先程の原さんの話にもありましたが、身体を介在していくというのはすごく大きな要素だと思います。
最近、モノと人との関わり、広い意味では空間と人の関わりの中で、必ずしも僕らは友好的な関係というわけではなくて、何かしらギャップがある中でぎすぎすしながら日々を過ごしているけれど、特にそのことが際立つのが衣服なのかな、と考えています。着なれない服を着ているときはやっぱり窮屈だし、気持ちよくない。衣服というものが、一番身近な空間だとすると、実は僕らは日常的に衣服を通して、最も身近なインスタレーション的な体験をしているかもしれない。そして逆に、大西さんの作品を観た時に、あの樹氷みたいなもののなかに身を置きたいなと思ったのは、着心地良さそうな服を見て、身にまといたいと思う感覚に近いのかも。そう考えると、インスタレーションには、僕らが普段忘れている身体的な感覚を呼び覚まして空間経験の原点を再確認させてくれるところがあるのかなという気がしました。京都ならでは夏の暑さとか、普段以上に不快感を認識しやすい時期の展覧会だったからということもあるかと思いますが、特に今回の大西さん、松澤さんの作品に感じた心地よさから、逆に本当に心地よい空間とは何だろうと改めて考える機会にもなりました。

加須屋:
身体感覚を通しての、衣服としてのインスタレーション的な空間の捉え方についてですが、大西さんの過去作、例えば国立国際美術館の『世界制作の方法』(2011)で展示でされていたような、接着剤でポリエチレンシートを吊るタイプの作品では、中には入れないにしても、その真下にいて体験することは可能ですよね。
大西:
はい。そうですね、黒い接着剤で山のようなかたちが吊られているタイプの作品には、中に人が入れるというか、人が内側と外側を観られるようなものがあります。でも、今回のに関しては、入っちゃ駄目なんです(笑)。虫の視点のような感じで中の方に入っていく様子を、目線でたどっていって、外側から想像するというか、向こう側の壁の景色を観る、というような。
加須屋:
メイキング映像のほうでは、割と中に入った感じが出ていて、結構楽しく拝見したんですけれども、それはそういう意図も入っていたのでしょうか?
大西:
映像を作った人にはそういう意図があったのかもしれないです。僕はそんな指示は出してないんですけれども。ジオラマを上のほうから俯瞰して観るとか、違う世界を観ているような感覚で見ることが出来るかもしれませんね。
加須屋:
心地よい空間をもとめて大西さんの作品を観ると入りたい、という欲望がうまれるんですけど、それは拒まれる。美術作品の場合に心地よさだけではない空間の体験を、また違った形で味わうというところがあると思います。そういう意味では大西さんの作品が欲望を掻き立てるんだけど充足はさせてくれないということで、より惹き付けるものがあるかもしれないし、あるいは何故なのかを深く考えさせられるところからまた違うものが見えてくるかもしれません。

加須屋:
松澤さんの今回の展示ですが、入ってすぐには、暗くて良く見えないんですけれど、じっと見ているまずは葉っぱが使われていることがわかる。これ白いのかな、とまたしばらく観察をしていると、目が慣れて来て、実はそれぞれ色がついている。このように、何段階かに分けて、最後にようやくいろんな色の違いが見えてきたときの喜びが、先ほど原さんがおっしゃっていた事象の連鎖、ということにつながるのかなとか思ったりしました。じわじわと味わっているうちに見えて来るという意味では、大西さんの展示は明るくて、入った時の印象も非常に大きいですが、結晶のひとつひとつをじっと見ているうちに、また違う風景が見えて来るという意味では、なにか時間をおきながら、違うものが見えて来る体験をさせてくれるという共通点があります。まずはある意味理屈としては非常に分かりやすく、親しみやすいものであって、しかも時間をおく間に様々な違う体験が出来たりする。いろいろ意味で可能性の広がる展示のひとつのありかたとして非常に面白いものだったかなと思います。
原:
その空間のなかに身をゆだねたときに、作家の意図的なものに嵌められていく感覚はありますね。今回の展示であれば、(大西さんの作品で)細い垂れたもののなかに何があるんだろうかとか、(松澤さんの作品で)その奥に何か潜んでいるものがあるんじゃないだろうかとか、入って行きたいという気持ちにさせたというのも、ある種、作家の思うつぼなのかもしれないし。照明にしても、過程にしても、そういう作り込みと言うか、そこでしかできないことだと思うんですよね。

作品の保存、再現性について
加須屋:
大西さんは海外での展示経験もたくさんお持ちですが、自分が日本で、あるいは関西で展示する場合と、海外の違う文化の文脈の中で展示をする場合で違うことはありますでしょうか?
大西:
そうですね、作品を観た時に、何か興味を持ってもらえる、簡単な第一印象が強烈で独特なものを作りたいと思っていて、それは別に日本、外国という線引きはしていないです。ただ、外国の方は「日本的」だと感じることもあるようなのですが。意識していないと言えばうそになるけれど、何かはそこにあるぐらいの感じですかね。ここ2,3年は、アーティスト・イン・レジデンスなどで、かなり制作期間を長くとってもらって最終的に展示をするのですが、それらはすべてその場限りのもので、終われば解体してしまうものです。
原:
インスタレーションという作品形態とか、その保存の問題、再現性を考えるとき、加須屋先生の初めのお話で、同じ作品を他の場所に持って行っても、全く同じものにはならないという話がありました。アーティスト自身がその作品のなかにある要素をうまく場に馴染ませていくことによって、違う新たな読み解き方みたいなものを引き出していくことはできますが、今後アーティストがこの世にいなくなった時に、その要素をそのままどこかに持っていって他の人が指示書通りにしたからといって本当にそうなるんだろうかというような問題があります。
鞍田:
例えば、ヨーゼフ・ボイスの作品などが展示されているのを観ると、それこそ指示書に従って並べてあるんでしょうけれど、標本を見ているみたいで全然わくわくしない。
加須屋:
おそらく御本人がいれば、空間との関係性などを考えながら作品を変化させていくところが、今となってはその指示書通りにするしく、作品自体が持っている様々な意味のなかのいくつかは失われているのかなと思います。今年ヴェネツィアで、1969年にハラルド・ゼーマンがキュレーションした『態度が形になる時』という展覧会が再現されました。アーカイブという意味では、写真ではなくて実際に空間の中で観ることが出来るというので、出来る限り忠実に再現されたことは素晴らしいとは思いながらも、それは先ほど鞍田先生がおっしゃられたように、標本みたいな、生き生きした躍動感に欠けるように感じられました。そういうものの再現をどうするかという問題はずっとありますよね。御本人が生きておられたとしても、例えば外国の方の作品を買った場合、インストラクションと一緒に保存して、展示する時には来ていただくのかそれともこちらでやるのかとか、或いは部屋ごと保存してしまうというやり方もあり、その場合も修復をどうするのかとかもあるのかと思いました。もちろん、一概に「インスタレーション」といっても、現在は様々なものにその言葉が使われていますので、タイプによって違うんじゃないかなと思いますけれども。
いま、「インスタレーション」と呼ばれるもの
原:
例えば、彫刻家の松井紫朗さんは作品を展示する際に、内部と外部、その関係を入れ子にしていったり、あるいは建物そのものを使いながら、と空間を非常に上手くお使いになるんですね。そういう意味ではインスタレーション的なものなのでしょうが、私のなかでは松井さんの作品は「彫刻」だと思っているんです。決して悪い意味で言っているのではなくて、そのフォルム、形をしっかり把握されてお作りになる過程は、彫刻として完結している。「インスタレーション」という言葉がここ数十年多用されてきて、絵画や彫刻とはまた別のものと捉えられているのですが、実際には、「インスタレーション」と呼ばれているけれど、本当にそうなのかというものもあったりするわけです。「インスタレーション」とは空間を構築していくことが全て、なのでしょうか?
大西:
「インスタレーション」かと言うのかどうか、というより作家自身がそうだという場合は全部「インスタレーション」と呼んであげればいいじゃないのかな、と思うんですが。逆に本人が、いやこれは彫刻なんだと言うなら彫刻に。僕自身の作品としては、そこまで何と呼ばれるか気にしていない感じがするんですけど、どうでしょうか。
加須屋:
ミロスワフ・バウカを例に挙げると、本人は自分は彫刻家であり自分が作っているのは彫刻で、「インスタレーション」とは呼んでくれるなと言っているのですけれども、それは仮設や一時的なものではなく、自分の作品は保存も出来るし再現も出来るということを強く主張したいからではないかなと思っています。ただ、彼も最初は彫刻的な立体作品を作っていましたが、最近の作品では映像を取り入れたインスタレーションが多いので、定義がずれていく、あるいは変化していっているかもしれませんが。だからその一時性や素材などに限らず、絵画や写真などの平面作品であっても、空間を強く意識しながら展示構成がなされている場合には、作家自身が「インスタレーション」と言ったり、こちらも「インスタレーション的な展示」という解釈をしたりすることは多々あります。だから定義することは非常に難しいんでしょうね。本題的には空間全体を身体で体験するかどうかということなのでしょうが、ただ様々な領域の境界線が曖昧になる中で、どんどん拡張しているのだと思います。